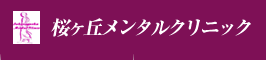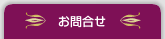 |
 |
桜ヶ丘メンタルクリニック
名古屋市千種区桜ヶ丘11
ソフィアビル2F
(星ヶ丘郵便局すぐ上)
電話
052-788-2100 |
 |
 |
 |
|
|
 |
2.『緩和ケア――精神分析になにができるか』の出版 |
 |

私(加藤誠)が翻訳しましたミッシェル・ルノー著『緩和ケア――精神分析になにができるか』が、2004年2月20日、岩波書店より出版されました。この翻訳は、私が名古屋掖済会病院に勤務していた頃、同病院で緩和ケア病棟ができるということを機にはじめたものです。途中、私が急遽クリニックを開業ということとなり、名古屋掖済会病院勤務当時に出版できなかったのは少し心残りですが、私の移動にはかかわりなく、ルノー氏のこの本はこれから多くの人たちに読まれるべき価値のある著作だと思っています。
この本は、ルノー氏がパリ第6大学の講師として、1995年から1996年にかけて、緩和ケアにたずさわろうとする医療従事者を対象にして、パリのブルッセ市民病院で6回にわたっておこなった講演の記録です。その内容は、精神分析家の立場から緩和ケアのあり方を論じたものですが、受講者たちは精神分析をよく知らない人たちであることを前提として語られていますので、専門的であったり、やたらに難解であったりすることはありません。平易な表現での講演となっています。
また、この本は、ある意味でとても実践的ではありますが、緩和ケアの実践の方法がマニュアル書的に書かれているのではありません。「死に行く人たちの心には何がおきているのだろうか、そしてそれはどうしてなのか」という問いが精神分析的観点からアプローチされ、そうした問いのもとで、死に行く人たちにはどのように接すればよいのだろうかということが、すぐれて倫理的な水準で論じられています。そして、これらの問いは、医療従事者だけにかかわりのあるものではないと思います。死に行く人を家族内で抱えていたり、死に行く人と接する機会のある人たちにとっても、重要な問いです。
さらに、「死に行く人たちの心には何がおきているのだろうか」という問いは、実は、老いた人たちだけの問題ではなく、すべての年代の人たちにかかわる問題でもあると思います。ここでは、この問いを哲学的に問うことが問題なのではありません。死というものをあえて意識的に問わなくても、死の問題は常に私たちの精神を規定しているからです。一見、死とは関係がないようにみえる不安であっても、実は死の不安が根底にあることもあります。また、精神分析でいうところの「去勢」の問題が、「死」というかたちをとって主体に課せられることもあります。それは例えば、不安という症状で現われる場合もあるでしょう。さまざまな不安がある中で、ルノー氏は、次のような例を挙げています。その女性は、癌の疑いで検査入院をしました。しかし、検査の結果は問題ないのに、主治医のちょっとしたしぐさや態度で、「自分は癌と宣告されるのではないか」と思い込んで不安に陥ってしまうのです。そのくだりを少し引用しましょう。
『検査は終わって安心し、看護師たちに囲まれてもいるにもかかわらず、なぜ、このような不可解な不安が起きたのでしょうか。
医療スタッフの対応に問題があったとか、患者の危惧に彼らが影響を与えたとかいうことは、この場合、まったくありませんでした。にもかかわらず、彼女の不安を呼び起こしたのは彼らだったのです。どのようにしてでしょうか。その科の主任医師ははじめから、自分の患者を安心させようと真剣に望む人間として、彼女の前に立ち現れていました。「私を信用してください。私はあなたを治療したいと思います。しかし、緊急事態が起きるかもしれません。でもそのときは、私はすぐに対応いたします」と彼は告げていました。
自分の病気について何も知らず、依存的にならざるをえない状況の中で、彼女は彼の治したいという欲望にすべてをゆだねていたのです。このとき、この医者のイメージは、かつて彼女の命を見守り続けていてくれた人たち、つまり、いつも暖かく救ってくれる母親や、力強く保護してくれる父親といった、救済者的な人物のイメージと重なっていたのでした。不幸にも、今述べたような重なる検査の遅れは、彼女に次々と疑念を抱かせたのでした。「もしあの医者が本当に私を救おうとしているのなら、そして事が緊急事態というのであれば、なぜこんな遅れが生じるのだろうか。なぜあの医者は、約束していた午後二時に来なかったのだろうか。私を救うことなど、どうでもいいことだったのだろうか。私の身にこれから起きるかもしれない事柄など、気にも留めていなかったのだろうか」などという疑念です。こうしたすべての疑念は、「知」と「力」に対する幼少時の絶対的依存の根源的状況を甦らせたのです。生まれたばかりのときの状態と同じく、患者は、「他者」が自分の状況を決定するという「他者」の絶対的力を前にしての自分自身の無力さに、再び直面せざるをえなかったのです。その医者の現実の人間性を超えたところにある、無意識の(不安の)対象は、彼女の記憶にまとわりついている前歴史的なこの「他者」によって、隠されています。そこには決定できない何かがあります。その何かから、不安が生じるのですが、「「他者」の欲望は何だろう?」という問いに、この不安は結びついています。「あの医者は、主任医師としての彼の始めの言葉どおり、本当に私の救済を望んでいるのだろうか。それとも、主任医師としての沈黙と不在は本当は「見捨て」のサインを表しており、そのサインのとおりに、あの医者は私が死んでしまうことを望んでいるのだろうか。つまりは、私がすべてをゆだね、私が生きのびるか死ぬかが懸かっている彼のあの欲望について、その真実はいかなるものなのだろうか」、などという問いが発せられるのです』 (第二章 「不安の概念をめぐって」より)
このあとルノー氏がどのように述べているかについては、直接、本にあたっていただくことと致します。
ただ、死の問題はすべての年代の人たちに関わり、人間の精神を規定しているということについて、すこし付け加えさせていただきます。死は、現代では遠ざけられ、忌み嫌われ、その一方で、戦争や犯罪などによって突然に引き起こされ、世界に報道され、「無残な象徴化できない」事態として私たちに伝えられます。こうした現代――現代といっても、数年前から始まったというような現代ではないのですが――の状況中で、死の問題、死の諸相は、さまざまな精神の「病理」をとおして露呈されてくるということもあると思います。たとえば、拒食症です。チエリー・ヴァンサン(Thierry Vincent)という精神科医であり、精神分析家である人は、『拒食症』(L’anorexie, Editions Odile Jacob, Paris, 2000)という本の中で、この点を詳述しています。この本の第5章「「遠ざけられた」死」のなかから、いくつかのくだりを抜粋して、以下に訳出してみることにします。
死の欲動の具現化としての拒食症
拒食症者が表しているものを理解するためには、死が遠ざけられている世界の中に彼女らをおいて考えてみなければならない。そうした世界の中で、彼女らは死の欲動をあらわに見せている。それに対し、かつての世界――当然、状況は違っていたが――では、ヒステリー者たちが性的欲動をあらわに見せていた。欲望を単なる欲求から切り離すために、拒食症者は、「飢えの欲望」を浮かび上がらせようとする。そのために、彼女は食べないことで「食べる対象の完全支配」を企て、欲望を成立させようとする。しかし、それは不可能な企てである。彼女は世界を、この「食べる対象」の次元へと還元する。すなわち、世界は「食べられるもの」となり、貪り食われるものとなる。〔貪り食う=呑み込み消してしまう=死をもたらしてしまう〕そのようにすることで、拒食症者は、沈黙のスクリーン上に死の欲動を映し出してしまう。それまでは、そのスクリーンの上で死の欲動は、リビドー的生の共通の表れの陰に隠れて活動していたのである。このように拒食症者は、他人のまなざしのもとに、この死の欲動を目に見えるものとして浮かび上がらせてしまう。
拒食症の全身衰弱に特有の、死体を思わせるような様相は、強制収容所から逃れてきた囚人の様相に似ている。(この比較は、患者たち自らによってひそかになされている。)あるいはまた、免疫抵抗力をなくした患者があらゆる日和見感染にさらされる、その様相に似ている。つまり、拒食症者の様相は、外的な理由にしろ内的な理由にしろ「死を宣告された」人たちに似ているのである。しかし、拒食症においては、「やせ」は、恥ずかしがらずにむしろ悦びの気持ちでもって人前にさらされる。だからこのことで、家族や看護する者たちにとっては、この病気は耐えがたい病となってしまう。言うならば、拒食症は死を具現化している。拒食症は、死を演じ、死に心を奪われ、死でもって身を飾り、死を踊らせる。死や死の苦しみが遠ざけられ、封じ込められている世界においては、拒食症は死を中心へと導き、死は生きている者たちのただ中にいつも存在していることを思い起こさせる。生きている者たちは、たとえそのことについて何も知ろうとはしないにせよ、「死に向かう存在」なのである。『死者は死んではいない。生者もまた生きてはいない。死ほど現実的なものはない。このような状況のなかで、拒食症者が試みていることは、死ぬことではなく、まさに死に行こうとする状態に近くなることである。つねに生きのびつつ、生のなかにある死に近づくことである』(1)。
(以下略)
注)(1)Ginette Rimbault, Clinique du reel, Paris, Le Seuil, 1982.
現代の死
かつては、死が生者の核心を握ってきた。しかし、19世紀に医学臨床が誕生し、その結果としての高度先進医療が到来してからは、生者が死を管理するようになり、その肉体の内部で、死を押し止めようとするゆっくりとした道を辿るようになった。死は、私たちが観察し、その到来を遅らせることのできる生物学的なプロセスとなってしまった。死はもはやひとつの到達点でしかない。すなわち、私たちが治療し、ときには治癒できる病気の到達点である。死は生から遠ざかり、もはや生きている人間的のものではない。死は、人間が生が終えた瞬間にしかやって来ない。死と死体の観察から出発した医学は、しかしもはや死について何も言うことがなくなってしまうであろう。なぜなら、死はもはや医学の関わることではないのであるから。だが、じっさい死が訪れたなら、それは、医学はその優れた技術や知識にもかかわらず敗北してしまったということである。死は、法医学的な敗北をふくめて、医学の敗北を告げるものである。死は科学と思考の敗北となっている。死は思考されることができず、せいぜいそれが近寄ってくることを把握することができるだけである。にもかかわらず、死はそのものとして、つまり思考不可能なものそれ自体としてあり続けるのだ。死はもはや生きている人間の中心にはなく、われわれがそれを閉じ込めてしまっている生の辺縁の中で彷徨している。
こうした急激な変化がなされるためには、もちろん、人間が人間自身に対してそそぐまなざしが大きく変化することが必要であった。死体を解剖するのも、古代の解剖学者や古代の身体病理学者たちがなしていたようにするのとは、意味が異なってしまった。つまり、死は肉体にわりあてられなければならなくなり、死が活動し始めるのをあえて見極めねばならなくなった。そして、知識の場それ自体にかかわる何千年にわたる禁止を踏みにじらねばならなかった。その禁止を侵犯することにより、まさしく人間は死すべきものとされたのであった。死はもはや神のみ業にかかわることではなく、人間の所業となってしまった。この点で、ここには根源的な両立不能性があるように思われる。私たちは死体を解剖しても、死体の中に神を見出すことはないであろう。さらには神を死体から追い出すことによって、科学者としての人間は、神にとって代わる場を占めようとする意志をあらわにしている。つまり、科学としての医学は人間の不死性を求めようとしている。医学の進歩は不死性へ向けての前進過程である。「今日それがかなえられなければ、あすにそれをとっておこう」とは、しつこく繰り返される決まり文句である。この決まり文句は、医学が治癒できない人たちや、医学により死が十分に押し止められない人たちに対して、現実的で非常に大きな意味をもってくる。
したがって、うまくコントロールされない極度の疼痛に苦しんでいる人たちについて嘆いても無駄であるのと同じように、先端医療が突然おろかな攻撃的治療法に転じてしまうことにより、先端医療自体によって患者が病院で孤独に死ぬこともある、ということを嘆いても無駄であろう。こうした先端医療による死は、「それを行う熱意は倫理的な賭けである以上、その熱意はひろく認められたものとなる」という論理の中に書き込まれているのである。この倫理的賭けとは、生きている者を、彼をとらえている死からできるだけ遠くに離して救ってあげる、たとえ彼が意識をなくしたり、植物人間状態になったとしても、救ってあげる、という賭けである。こうした状況の中では、一秒でも延命できたなら、それは勝利である。しかしその勝利は、苦しむ患者の勝利ではなく、患者の背後にいて、生き続けるために戦ってくれた、医療スタッフたち全体の勝利である。死は受け入れられがたいものであるゆえに、最後のカード(死)をめくって、そのカードを次の人にわたすのを禁じられてしまった人にとっては、死は忌むべきものとなり、一撃に等しいものとなる。
死は、考えから遠ざけられ、家族によって隠され、身近な人たちからは差し引かれる。私たちは死者に死者を埋葬させ、そしてなにより、死を避けてほかの事柄へと向かわねばならない。このようにして、喪のための服装や装飾や儀式はどんどん疎遠になってゆき、死者たちを思って泣くことも見せられなくなり、死に行く人々に家族が最後まで付き添うことも難しくなってゆく。このように、喪を遠ざけておいて、悲しみや自失状態が少し過度だったり、長く続いたりすると、それらは病的なものとして扱われてしまうのである。精神分析家たちは、こうした悲しみや自失状態についての証人であり、それを証言することができるであろう。フロイトは20世紀のはじめに、『喪とメランコリー』という著作の中で、「抑うつ状態とは喪の悲しみの状態である」と言い、その後、メラニー・クラインは、この同じ臨床問題をとりあげて、「喪の悲しみは抑うつ状態のことである」と書いている。
かつて大人たちが子供たちを、性の問題や、赤ちゃんはどうして生まれるかという謎から遠ざけていたのと同じように、現代においては、大人たちは子供たちを、死や、人はいつか必ず死ぬということから遠ざけている。したがって、子供たちは思春期になって、自ら死を発見するという重荷を背負わされることになる。医学の進歩は、喪の悲しみを子供が発見することを遅らせてしまう。私たちは、私たちの身近な人たちの死に向き合うことをますます後回しにしてしまう。身近な人たちの死が、何らかの原因によって早く訪れてしまったときには、その早く訪れた死は、あらかじめ予期されず、考えられず、そしてなによりそれは考えられなかっただけ、その死は私たちにとって耐え難いものとなる。
(以下略)
(引用おわり)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
「考えられなかった死」と、ここでヴァンサン氏は書いていますが、そもそも、死とは考えられることの向こう側にあること、考えられることからは限りなく遠い所にあるものではないでしょうか。フロイトは、1915年に書かれた『戦争と死に関する時評』の中で、「私たちは自分自身の死を思い描くことはできない。無意識においては、私たちは自分自身は死なないと確信している」と述べています。確かに、現代は死を遠ざけ、日常生活の中からひそかに死を「隠蔽」してしまっていますが、同時に、私たちの無意識は自分自身の死を排除してしまっています。こうした状況の中で、現代に必要とされている「死を思う」とは、いったいどういうことなのでしょうか。これは各人に託されている問いです。
|
|
| |
|
 |
うつ病、パニック障害、全般性不安障害、抑うつ神経症、心気症、対人恐怖症、悲哀反応、ストレス反応、
強迫性障害(強迫神経症)、
拒食症・過食症、統合失調症、広汎性発達障害、
睡眠障害などの精神疾患の健康相談と治療。 |
|